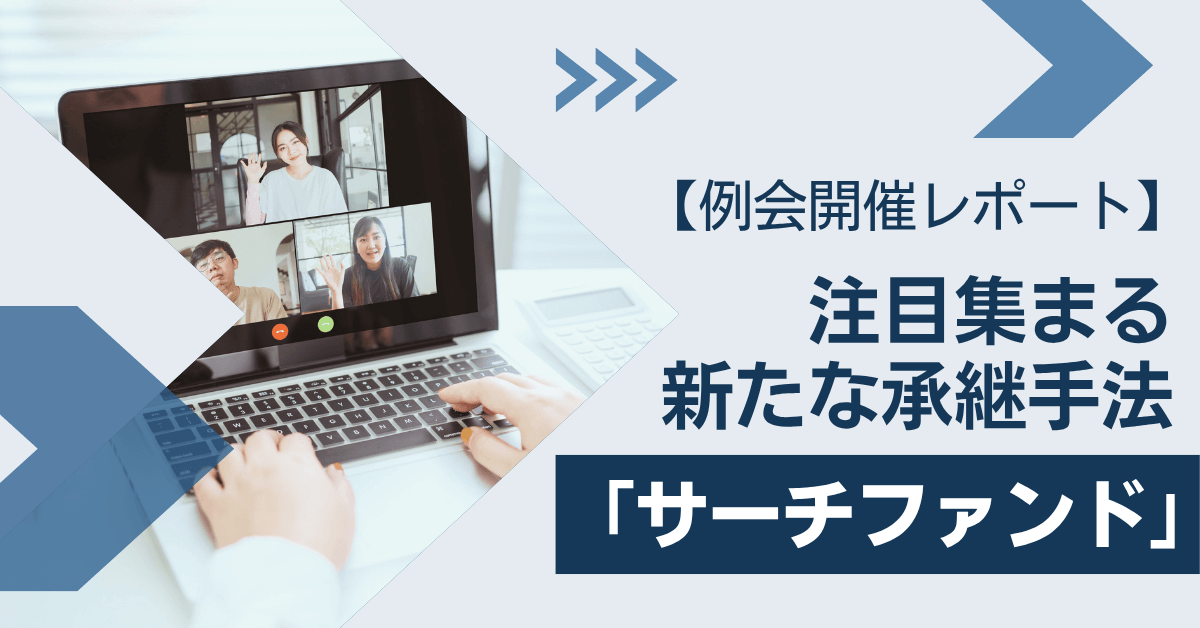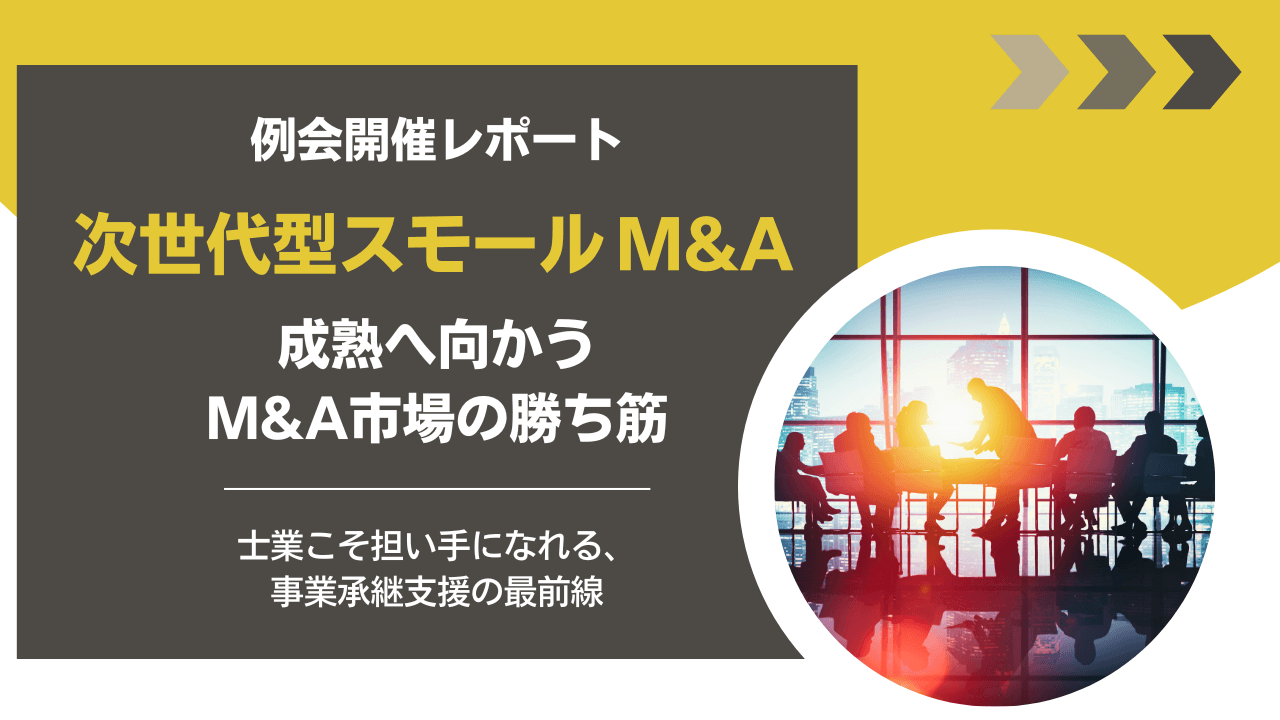はじめに
事業承継や成長戦略としての中小企業 M&A は、いまや特別な選択肢ではなくなりました。一方、市場が急拡大するスピードに対してルール整備が追いつかず、高額な手数料や情報格差を背景としたトラブルが後を絶たないのも事実です。
本稿では、不動産業界で宅地建物取引士(宅建)が誕生し、段階的に義務化へと発展した歴史をヒントに、“もし資格制度が導入されたらどうなるか” を整理いたします。士業ネットワークがどのように関わり、企業オーナーへどんな安心を提供できるのかも併せて考察いたします。
資格制度はどのように組み立てられるのか(予想)

現在示されている情報は限られていますが、宅地建物取引士(宅建)が「登録制 → 免許制 → 専任有資格者義務」と段階的に強化された歴史をふまえると、中小企業M&Aアドバイザー資格も「任意資格でスタートし、数年後に一定規模以上の案件で必須化」という流れをたどる可能性が高いと考えられます。
以下に、想定される主な制度設計と期待されるメリットをまとめました。
| 項目 | 想定される方向性 | 期待できるメリット |
| 試験方式 | CBT(コンピュータ試験)またはマークシート方式で、財務・税務・法務・PMI 基礎を総合出題 | 支援者の最低限の知識水準を可視化し、企業オーナーの安心感を高めます |
|---|---|---|
| 倫理・更新 | 行動規範の遵守を義務づけ、定期講習・更新制と違反時の登録抹消措置を導入 | 利益相反を抑止し、消費者(売り手・買い手)の保護を強化します |
| 登録データベース | 公式サイトで有資格者検索が可能(地域・専門分野・実績などで絞り込み) | 経営者が適切な相談先を選びやすくなり、地域偏在の解消にもつながります |
| ガイドライン連動 | 「複数機関への相談」を制度的に後押しし、セカンドオピニオンを標準化 | 二重チェックが普及し、過剰手数料や恣意的な条件提示を防ぎます |
このような枠組みが整えば、資格者にはデジタルバッジの発行や定期 CPD(継続専門研修)の義務づけが想定され、最新の税制改正や M&A 実務のアップデートを学び続ける仕組みが動き出します。
さらに、地方の中小企業でもオンライン相談を活用して都市部の専門家にアクセスできるようになり、情報格差の解消が進むと期待されます。
セカンドオピニオンが標準化するかもしれない理由
中小企業庁が公表した 「中小 M&A ガイドライン(第3版)」 では、
「仲介者や FA だけに頼り切らず、第三者の意見も取り入れること」
を強く推奨しております。資格制度が創設され、公式サイトで有資格アドバイザーの一覧や専門分野、実績が検索できるようになれば、経営者は次のような「ちょっとした見直し」を気軽に依頼できるようになるでしょう。
- 条件の再確認(買い手/売り手双方の利害が公平か)
- 手数料水準の妥当性チェック
- 企業価値算定のセカンドチェック
これにより、情報格差や過大手数料が生まれにくくなり、市場全体の健全性が高まると期待されます。
さらに、金融機関が融資審査の一環として「第三者意見書」の提出を推奨する可能性もあり、その場合はセカンドオピニオン取得が“推奨”から“ほぼ必須”へと位置づけが変わるかもしれません。
公開データベースが整備されれば、地方の経営者でもオンライン面談を通じて都市部の専門家と簡単につながるようになります。
結果として、「相談先が見つからない」「誰を信じれば良いかわからない」といった不安が大幅に緩和され、M&A に踏み切る企業が増えることも期待できます。
当研究会が果たす役割 ― 資格創設時代の“補助線”としての士業チーム
2026 年に創設が検討されている「中小企業 M&A アドバイザー資格」は、支援者の知識や倫理を“見える化”し、経営者が相談先を選びやすくする仕組みになると期待されています。
けれども、資格を持つだけでは 「ディールが終われば役目も終わり」という従来型の支援を抜け出せません。
| フェーズ | 主なサポート内容 | 関与士業例 | 資格制度と組み合わせた価値 |
| 検討・準備 | 後継者の有無確認、財務・組織の「見える化」 | 中小企業診断士・税理士 | 資格取得者による中立診断+複数士業の相互チェック |
|---|---|---|---|
| 実行(DD〜契約) | 財務・法務・労務 DD、条件調整の助言 | 会計士・弁護士・社労士 | デューデリ結果を資格者 DBに基づく第三者が検証し透明性を担保 |
| 統合(PMI) | 組織再編、ガバナンス・労務体制の整備 | 診断士・社労士 | 資格者が作成した統合計画書を各専門家がフォローアップ |
| モニタリング | KPI チェック、課題抽出・改善提案 | 各士業合同レビュー | 資格更新 CPDの一環として改善事例を共有し、学びを循環 |
- 内部承継が可能な場合は、それを最優先に選択できるよう、育成計画や株価対策を徹底支援いたします。
- 外部承継が最適解となる場合でも、資格者の行動規範に則った透明なプロセスで進め、「買い手・売り手・従業員」すべてに安心をお届けします。
資格制度をにらみ、いま“情報”と“学び”に集中する2つの準備

中小企業M&A アドバイザー資格が正式に発足すれば、試験範囲・倫理規程・更新要件などが短期間で固まります。
1.最新情報を継続ウォッチする
- パブリックコメント、審議会資料、省庁・業界団体リリースを定点観測し、「試験範囲」「行動規範」「登録・更新要件」の改訂履歴をタイムラインで整理します。
- 特に 試験シラバス案・倫理規程案・CPD(継続研修)要件案 はアップデート頻度が高いため、変化点を色付きでハイライトし「何を勉強・準備すべきか」を月次で棚卸しすると効果的です。
2.専門外の基礎知識を横断的に深める
- 資格試験では 財務・税務・法務・労務・PMI が横断的に問われます。自分の専門領域以外については“用語と概念を説明できるレベル”を最低ラインに設定し、ショート勉強会やケース共有で底上げを図りましょう。
- 具体的には、
- 「30 分でわかる企業価値算定」 などミニ講座を持ち回りで開催。
- 他士業が作成したチェックリストや報告書を読み込み、「なぜその項目が必要か」をディスカッション。
- ガイドライン違反・利益相反の事例をロールプレイし、倫理判断の基準を体で覚える。
- こうした横断学習は、資格取得後の CPD 対応 にも直結し、チーム全体のサービス品質を底上げします。
情報を逃さず、知識の“スキマ”を埋める。
この2点に絞って先行投資しておけば、制度開始と同時に「資格+実務力」を堂々と提示できるはずです。これを実現するためには当研究会への参加することが近道になります。
おわりに
資格制度が本格的に動き出しますと、M&A 支援の世界は 「見える化」と「多層化」 が一気に進みます。
経営者は複数の窓口を比較して選べるようになる一方、支援側には明確な役割分担と密な協働が欠かせません。
私たちスモール M&A 研究会は、中立・非営利の立場で
- 取引前の不安整理
- 取引中の適切な助言
- 取引後の円滑な統合
を静かに支える“縁の下の力持ち”でありたいと考えております。
「最終契約書にサインする前に、もう一人の専門家の目を」
今後は資格創設に合わせ、ガイドラインに準拠したチェックリストや統合後 100 日プランのテンプレートを無償公開する予定です。さらに、会員同士で最新判例や補助金情報を共有するオンライン勉強会を毎月開催し、地方と都市の情報格差を埋める取り組みも強化いたします。
ご関心のある士業の皆さま、そして事業承継や M&A を検討されている経営者の皆さまは、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆さまと共に、安心して挑戦できる地域経済の未来を築いてまいります。
🟢 スモールM&Aに関するご相談について
スモールM&A研究会では、中小企業の皆さまが安心して事業承継・M&Aに向き合えるよう、専門家同士のネットワークを活かした情報提供やご相談対応を行っています。
直接的な営利を目的にはせず、公正で中立的な立場から、経営者の意思決定を支えることを大切にしています。
- 事業承継やM&Aの検討を始めたばかりの段階でも構いません
- 士業や実務家と連携した多面的な視点でご相談に対応
- ご相談内容・個人情報は厳格に守秘します
中小企業診断士 田中 寛也 (Hiroya Tanaka)
当研究会代表/株式会社タタアイズ 代表取締役(https://tataeyes.co.jp/)

建設業を中心に、地域の中小企業を支援している経営コンサルタント。
経営改善や事業承継のご相談を多くいただく中で、近年はスモールM&AにおけるFA的な立場での支援にも力を入れています。
士業や金融機関とのネットワークを活かしながら、「誰に相談すればよいか分からない」という経営者の不安に寄り添い、想いをつなぐM&Aの実現を目指して日々活動しています。
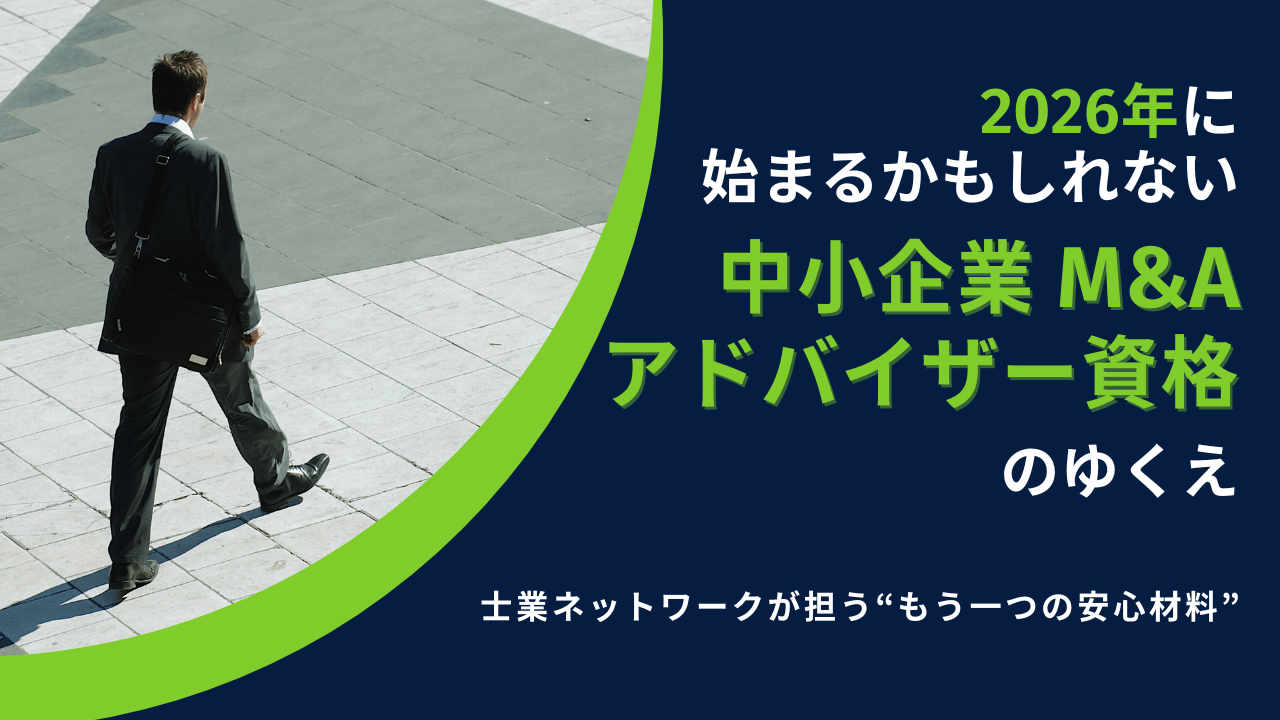


」のすすめ.png)