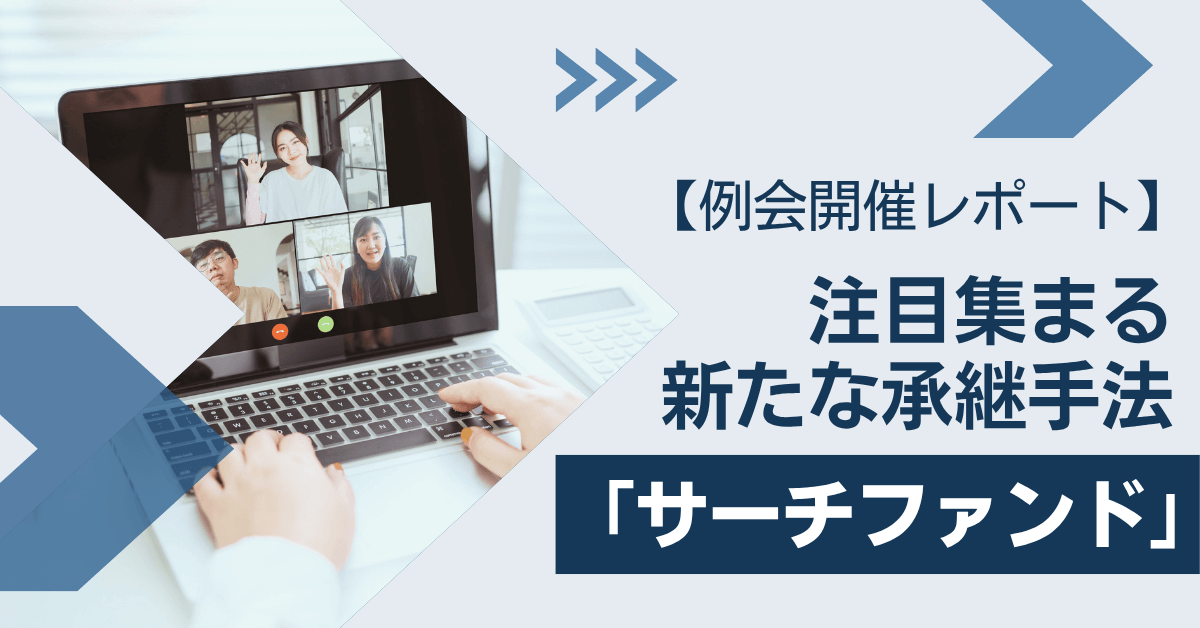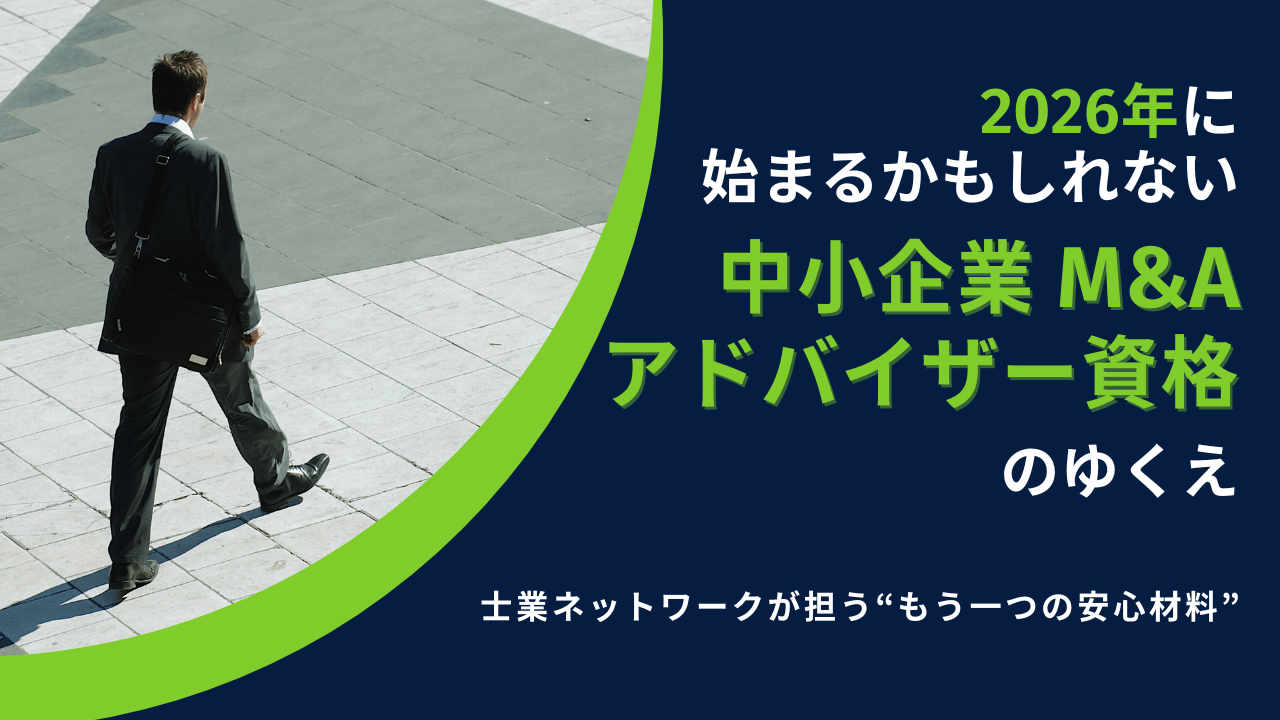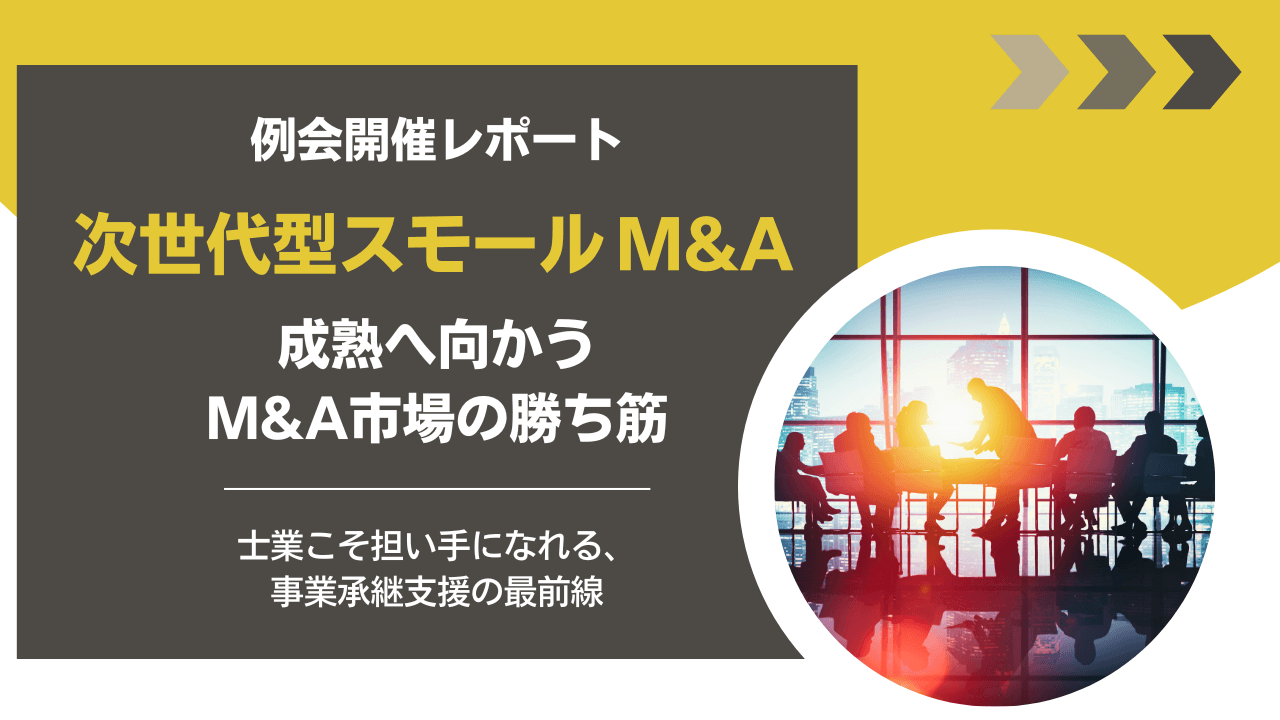近年、少子高齢化や後継者不在といった構造的課題を背景に、中小企業のM&A(事業承継)が全国的に加速しています。
中でも注目されているのが、売却額・年商・純資産いずれも3億円以下の「スモールM&A」です。いわば、より現実的で身近な“出口戦略”として、今後も取引件数の増加が見込まれています。
こうしたスモールM&Aの現場において、経営者が直面しやすいのが「FAと仲介、どちらを選ぶべきか?」という選択の悩みです。
本記事では、スモールM&AにおけるFAと仲介の違いを明確にしたうえで、案件規模や目的に応じた支援者選びのポイントを、現場視点から解説します。
FAと仲介の基本的な違いとは?

まずは、FA(ファイナンシャルアドバイザー)と仲介業者、それぞれの特徴を整理してみましょう。
| 項目 | FA(ファイナンシャルアドバイザー) | 仲介業者(M&A仲介) |
| 立場 | 売り手または買い手、どちらか一方の代理人(片手型) | 売り手と買い手の中立的立場(両手型) |
|---|---|---|
| 報酬体系 | クライアントからの報酬(着手金+成功報酬) | 双方からの成功報酬 |
| 目的 | クライアントの利益最大化 | 成立を最優先(中立的合意形成) |
| 交渉姿勢 | クライアントの利益を守るために積極的に交渉 | 双方の妥協点を調整 |
| 案件規模 | 主に10~20億円以上の中堅~大規模M&A | 小規模案件にも柔軟に対応(数千万円~10億円) |
FAは一方の利益を最大化する「代理人型の支援者」として、戦略的にM&Aを主導します。
一方、仲介業者は中立的な調整者として、合意形成と迅速な成立にフォーカスします。
「FA」の活用が効果的なケース
以下のようなケースでは、仲介よりもFAのほうが適している可能性が高くなります。
- 買い手候補を複数比較し、最適な相手を選びたい場合
→ 価格だけでなく、理念や相性も踏まえた選定が可能。 - 雇用や取引先の維持、ブランド継承など非財務条件を重視する場合
→ 仲介では扱いにくい細かな交渉まで踏み込める。 - 買い手側との情報格差が大きく、戦略的に交渉したい場合
→ M&A経験豊富な買い手に対し、FAが“対抗軸”となる。 - 入札形式や競争原理を活かして、価格や条件を引き上げたい場合
→ FAが主導することで、競争環境の構築が可能。
スモールM&AにおけるFAの「4つの役割」
とくに初めてM&Aに取り組む中小企業オーナーにとって、FAの以下の4つの役割は非常に重要です。
- 深い企業分析
財務・事業・人材など多面的に分析し、企業価値を明確化。 - 買い手同士の競争環境づくり
複数の候補者を巻き込み、交渉に競争原理を持ち込む。 - 有利な条件交渉の支援
金額だけでなく、雇用維持や社名存続など非財務条件も交渉。 - 広域ネットワークによる買い手探索
業界・地域を超えて、最適な買い手候補を提案可能。
FAが力を発揮するための“2つの前提条件”
ただし、FAを選べば必ず成功するわけではありません。
以下の2点は、FAを効果的に活用するための前提条件です。
- FA自身に高い専門性と実績があること
未経験のFAでは、逆に交渉や戦略設計が不十分になるリスクも。 - 買い手にもFAがついている、またはM&Aの知識があること
知識レベルに差があると、交渉が不均衡になりやすい。
士業ネットワークが担う“地域密着型FA”
スモールM&Aでは、税理士・中小企業診断士・社労士などの士業ネットワークがFA的な役割を果たすことが多くなっています。
売却金額別|FAと仲介の使い分け目安

| 売却金額 | 推奨スキーム | 理由 |
| ~1億円 | 仲介が現実的 | 買い手数が限られ、FAの戦略やネットワークが活かしにくい |
|---|---|---|
| 1~10億円 | 仲介+FAも選択肢 | 案件特性・目的次第ではFAの介入が条件改善につながることもある |
| 10億円以上 | FA推奨 | 戦略的交渉・入札・競争原理の活用で価格引き上げが期待できる |
このように、案件の規模・目的・条件交渉の複雑さに応じて、FAと仲介を使い分けることが重要です。
スモールM&AでもFA活用が進む理由
以下の理由から、今後はスモールM&AでもFAの活用がさらに進むと予想されます。
- 売り手側の情報武装ニーズが高まっている
相場感を知りたい、複数候補と比較したいというニーズが顕在化。 - 中小企業向けのFA人材が増加している
大手だけでなく、スモールM&Aに対応可能な専門家が参入。 - 非財務的要素(想い・理念・雇用など)の重視が進んでいる
単なる金額ではなく、“想いの承継”をサポートする力が求められる。
FA契約を選ぶ際の注意点
「FA契約」と書かれていても、実際には仲介的な動きをするケースもあります。
表面上の契約形態よりも、“実態”を見極めることが重要です。
- 案件への関与度合(着手からクロージングまで一貫支援か)
- 情報の開示姿勢と透明性
- 支援方針が自社の目的と一致しているか
- 対応スピードと柔軟性
まとめ:慎重に“支援者”を選ぶ
M&Aは、経営者にとって人生でも最大級の意思決定です。
価格やスピードだけでなく、「誰に支援を任せるか」が、企業と従業員の未来を大きく左右します。
- FAは、戦略性と交渉力に優れたプロフェッショナル型伴走者
- 仲介は、中立性とスピードに強みを持つ調整型実務者
スモールM&Aこそ、目的や背景に応じた支援者選びが成功の鍵となります。
事業承継・M&Aに関連するご相談について
スモールM&A研究会では、中小企業の皆さまが安心して事業承継・M&Aに向き合えるよう、専門家同士のネットワークを活かした情報提供やご相談対応を行っています。
直接的な営利を目的にはせず、公正で中立的な立場から、経営者の意思決定を支えることを大切にしています。
- 事業承継やM&Aの検討を始めたばかりの段階でも構いません
- 士業や実務家と連携した多面的な視点でご相談に対応
- ご相談内容・個人情報は厳格に守秘します
中小企業診断士 田中 寛也 (Hiroya Tanaka)
当研究会代表/株式会社タタアイズ 代表取締役(https://tataeyes.co.jp/)

建設業を中心に、地域の中小企業を支援している経営コンサルタント。
経営改善や事業承継のご相談を多くいただく中で、近年はスモールM&AにおけるFA的な立場での支援にも力を入れています。
士業や金融機関とのネットワークを活かしながら、「誰に相談すればよいか分からない」という経営者の不安に寄り添い、想いをつなぐM&Aの実現を目指して日々活動しています。


」のすすめ.png)